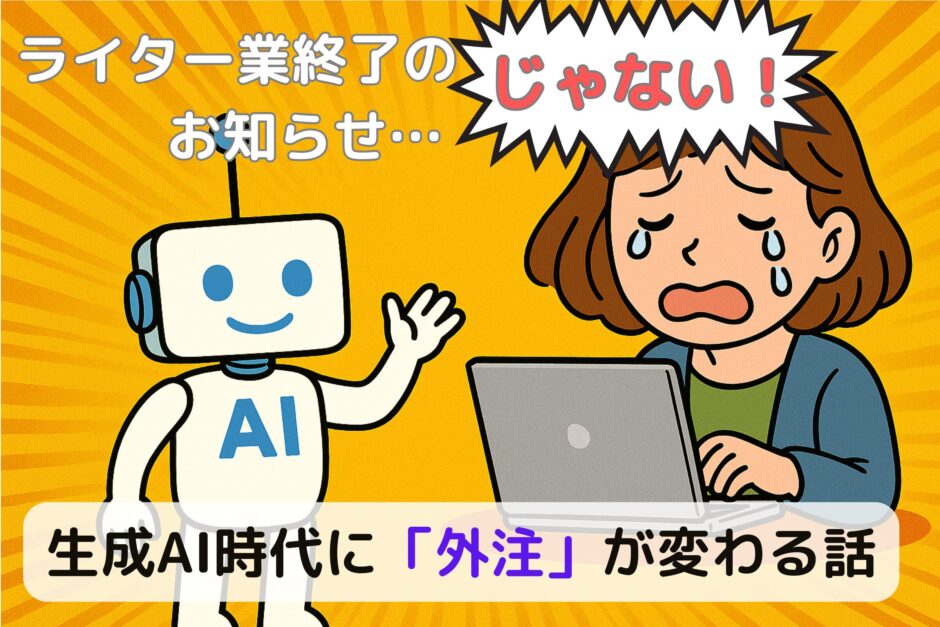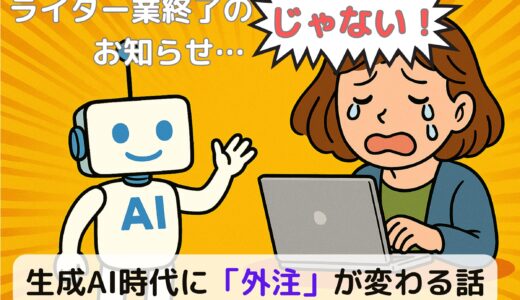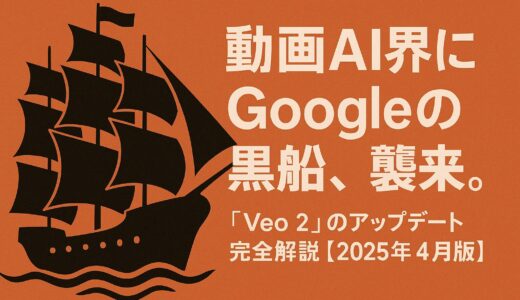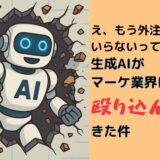え?このタイトル、これ書いてる人にも刺さるんじゃね?
──その通りです。
ChatGPTが登場してからというもの、「もう記事ってAIが書けるんじゃないの?」という声を、そこかしこで耳にするようになりました。特にここ最近の生成AIの進化ぶりときたら凄まじく、「人が書く意味って…?」と一度は考えた方も多いのではないでしょうか。
企業の広報担当にとっては「コストをかけて外注する意味ある?」という疑問が。
現役ライターにとっては「このままじゃ仕事なくなるかも…」という不安が。
じわじわ、でも確実に、心のどこかに居座っているはずです。
でもご安心を。この記事は「ライター業終了のお知らせ」ではありません。
むしろ本題はその逆。生成AIの台頭によって“外注の形”が変わる今、ライターという職業がどう進化すれば生き残れるのか?そして企業側はどんな判断軸を持てばいいのか?というリアルな話を、お届けします。
というわけで、この記事では次のような方に向けて、生成AI時代のライティング業界の今とこれからを、やさしく、でもしっかりと掘り下げていきます。
- 自社コンテンツをAIで内製化できないか模索している広報・マーケ担当者
- AIの進化に不安を感じながらも、文章を書く仕事を続けたいライターさん
「もう人間いらないじゃん!」と思われがちなこの時代に、あえて言います。
人間、まだまだ全然、必要です。わしらはまだやれます。
ただし、“やり方”は変わります。では、見ていきましょう。
1. 生成AIで「文章を書くこと」はどう変わったのか?
◆「AIで文章が書ける時代」は、もう現実
「AIが文章を書くなんて、どうせお粗末な内容でしょ?」と思っていたのは、もはや過去の話。
ChatGPTをはじめとする生成AIを使ってみた人なら、一度はこう感じたことがあるはずです。
「……あれ、これ、想像よりずっと書けてる。」
実際、すでにAIを業務レベルで導入している企業は多数存在します。
- AP通信:企業の決算報告をAIで自動生成。人間の記者は最終チェックのみ
- Amazon:レビューやSNS投稿をAIが分析し、売れる商品説明文を自動生成
- HubSpot:AIが構成~初稿までを生成し、人間が編集して仕上げるスタイルを採用
これらは「AIをちょっと活用」どころではなく、業務フローの中核にAIが組み込まれている例です。
◆スピード・量・“まあまあの質”の三拍子がそろう
生成AIの文章作成は、次の3点で圧倒的な強みを持っています。
- 爆速で書ける:数十秒〜数分で、指定ワード入りの文章が完成
- 大量に生成できる:何本でも繰り返し出力可能。AIは疲れない
- 意外と上手い:特にSEO記事やレポートなど定型文に強い
たとえば「〇〇というキーワードで、導入・見出し・まとめを含むSEO記事を書いて」と指示すれば、人間が1〜2時間かかる作業を数分でこなすことも。
さらに、文調を「やさしく」「固めに」などと調整することも可能です。
◆とはいえ、人間がいらないわけじゃない
もちろん万能ではありません。生成された文章には…
- 事実誤認や根拠のない記述
- やや不自然な言い回し
- 個性や感情の薄さ
…といった課題もあります。そのため、AIが出したドラフトを人間がチェック&編集するという流れが基本。
とはいえ、このスタイルに慣れてくると多くの人がこう感じます。
「ゼロから書くより、AIに下書きさせた方が断然ラク」
そしてこれが、多くの企業にとって「外注せずに内製できるかも…」という発想へつながっていくのです。

技術の発達とともに仕事の在り方はかわっていくにゃ
◆“全部自分で書く時代”から“AIに書かせて整える時代”へ
ライティングの現場は今、「100%手書き」から「AIドラフト+人間仕上げ」へと大きく舵を切り始めています。
これまでライターが担っていた「素早く、大量に、型通りに書く」仕事の多くが、AIによって代替可能な領域に突入しました。
次の章では、そんな時代に「企業はなぜライティング外注を見直しているのか?」を掘り下げていきます。
2. 企業はなぜライティング外注を見直し始めているのか?
◆外注ライティング=地味に高コスト
ライティングの外注って、案外お金がかかります。
たとえばSEO記事1本で1万円〜3万円、中には5万円を超える案件も珍しくありません。
これを「月10本」「年間120本」なんてペースで発注すれば、年数百万円規模の出費になります。
しかも出費だけじゃない。
発注にはライター探し、条件のすり合わせ、構成共有、修正依頼…とにかく手間がかかる。
広報やマーケの担当者が本来注力したい「戦略設計」や「分析」に手が回らなくなることも。
こうした“見えにくいコスト”が、少しずつ企業に効いてきているのです。
◆生成AIなら、コストも手間も大幅カット
ここで登場するのが、ChatGPTやClaudeのような生成AI。
プロンプト(指示文)さえ工夫すれば、AIがそれっぽい文章をサクッと作ってくれます。
たとえば、こんなイメージ:
「◯◯というテーマでSEO記事を書いて。構成は導入・見出し・まとめ。語調は丁寧でカジュアルに。3,000字くらい」
これで5分後には下書き完成、というのも夢じゃありません。
AIツールの利用料は月数千円〜数万円。
つまり、数記事分の外注費で1年分のライティング環境が整うのです。
さらにAIなら、納期調整や修正依頼も不要。
24時間365日、従順に働き続けてくれる“文章マシン”といっても過言ではありません。
◆「誰に頼むか」問題が消える
外注ライターを選ぶとき、多くの企業が頭を抱えます。
「この人、うちのトーンに合うかな?」
「構成力はあるけど、専門性が薄いかも?」
「前は良かったけど、今回はちょっとズレてるな…」など、“相性ガチャ”問題はつきものです。
でも、AIならプロンプト次第で調整可能。
一度「うちっぽい語り口」を学習させれば、毎回ブレない文体で原稿を出力してくれます。
人に頼むより“クセがない”という意味では、安心感すらあります。
◆「あれ、外注いらなくない?」という気付き
こうしてみると、企業がふと考えるのも無理はありません。
「あれ?これ、いちいち外注する意味ある…?」
もちろん、すべてをAIに任せられるわけではありませんが、
「コスト・時間・人材リスク」の三重苦を抱える外注より、AIのほうが軽やかでコントロールしやすいのは確かです。
だからこそ、今、企業の中で
“外注不要論”という静かな見直しの波が起こっているのです。
3. それでもライターが「不要」にならない理由
◆AIが苦手なもの、それは“人間らしさ”
どれだけ優秀な生成AIでも、「人間らしさ」を自然に出すことは苦手です。
たとえば──
- 実体験に基づくリアルなレビュー
- 心の機微を丁寧に描いたストーリー
- 思わずクスッと笑ってしまうユーモア
こういった要素は、テンプレートや知識では出せません。
感情・空気感・文化的文脈といった、言語の“行間”を読む能力こそが、人間ライターの強みです。
◆独自データ・専門知識には人の手が必要
AIはネット上の情報をベースに文章を組み立てます。
つまり、「まだネットに載ってない情報」は書けません。
たとえば──
- 自社独自の調査結果に基づいた記事
- 社内の専門家へのインタビュー記事
- 特定の業界に特化した深掘り記事
こういった“現場の声”や“ナマの情報”を扱うコンテンツは、今もそしてこれからも、人間の取材と理解力が不可欠です。

人にしかできないことはまだまだたくさんにゃ!
◆「E-E-A-T」重視の時代、信頼できる人の声が強い
Google検索では現在、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)という評価基準が重視されています。
- 経験(Experience):実際にやったことがあるか
- 専門性(Expertise):その分野の専門家か
- 権威性(Authoritativeness):社会的に認められているか
- 信頼性(Trustworthiness):正確で安全か
つまり、「誰が書いたか」「どんな立場で書いているか」が問われる時代です。
AIが書いた無署名の記事よりも、名前と顔のある人間が書いた記事のほうが圧倒的に信用されるのです。
◆文章の“引き算”や“間”は、まだ人間の領域
AIの文章には、どこか「説明しすぎ」「文字数多め」「スベらないけど光らない」感があります。
一方で人間のライターは、意図的に“余白”や“遊び”をつくることができる。
- 「あえて書かない」ことで読者に想像させる
- リズムや間で感情を揺さぶる
- 行間に含みを持たせる言葉選び
こうした“テクニックではなく感覚”の領域は、まだAIには真似できません。
◆ライターの価値は「書く」から「伝える」へ
これからの時代、ライターの役割は単に「書く人」ではなく、
「AIが書いた文章を整える人」「人間の感性を通して伝える人」へと変化していきます。
むしろ、そうした視点を持つ書き手こそが、企業から選ばれる時代に突入しているのです。
4. 変わる「外注」の形と、求められるライター像
◆“まるっと外注”の時代は終わるかもしれない
これまでは、
「構成も執筆も全部お願い!」というフルパッケージ型の外注が主流でした。
でも今は、AIが下書きを生成→人間が仕上げるという流れが増加中。
となると、ライターに依頼される業務内容も変わってきます。
たとえば──
- AIが出力した文章のリライトや整文
- AIでは拾えない「人間的な視点」の追記・補完
- 企業のトーンや読者層に合わせた文体調整
こうした“仕上げ職人”としてのライター需要がじわじわ増えているのです。
◆求められるのは「AIと協働できる人」
正直、これからのライターに「AI使えません」はかなりキツい。
生成AI時代の今、企業が求めているのはこういう書き手です:
- AIでたたき台を作れる人
- AIに的確なプロンプト(指示)を出せる人
- AIの文章を人間らしく整えられる人
つまり、「AI×ライター」=最強という発想に企業はシフトし始めています。

鬼に金棒にゃ!
◆プロンプト力と編集力が“ライターの武器”になる
昔は「構成力」や「文法の正確さ」がライターの武器でしたが、
今後はそれに加えて、次のようなスキルが重視されるようになります。
- プロンプト設計力:AIに“意図を正確に伝える”技術
- 編集スキル:AI出力の文章を読みやすく整える力
- 文体調整力:企業のトーンやターゲットに合わせる感覚
これらは、AIを使えば使うほど差がつく“人間スキル”でもあります。
◆「人間らしさ」を盛れる人が選ばれる
AIは便利ですが、やっぱり「ちょっと薄味」な文章になりがち。
だからこそ、ライターには“にんげん味”を加えるスパイス担当としての役割が期待されています。
- 実体験や感情を絡めた導入文
- あえて“くどく”して笑いを取りに行く小ネタ
- 読者の心をふっと揺らす言い回し
これ、全部AIにはできません。
「味付け職人」としてのライターがこれからの外注市場で求められるのです。
◆AIの時代だからこそ、“ライターの再定義”が始まっている
外注はなくなるのではなく、「中身が変わる」のです。
- 書く量より、整える力
- 早さより、共感を引き出す表現
- 誰にでも書ける文章ではなく、「あなたにお願いしたい」文章
つまり、ライターは今まさに、「単なる外注パーツ」から
“選ばれるパートナー”へと進化中なのです。
5. 広報担当・ライターが今やるべき3つのこと
◆1. 広報担当は「外注の棚卸し」と「AI活用の検証」を
まず企業の広報・マーケティング担当がやるべきことは、自社で発注しているライティング業務の棚卸しです。
- ルーティン的なSEO記事
- 社内報やお知らせ
- メールマガジンや販促文面
- コラムや専門記事
このうち、「AIで書けそうなもの」と「人じゃなきゃ無理なもの」を一度整理してみることをおすすめします。
そして「AIにやらせたらどれくらいイケるのか?」を、一度試してみる。
ChatGPTやClaude、Notion AIなどを使えば、初期コストを抑えてトライアル可能です。
重要なのは、“全部置き換える”のではなく“上手く使い分ける”という発想を持つことです。
◆2. ライターは「AIスキル」と「にんげん味」の両立を
ライター側にとっての最優先事項は、AIを拒まず、使いこなすこと。
- プロンプトの組み立て方を学ぶ
- 文章構成をAIに任せて時短する
- AIの原稿を“自分らしい声”で磨き上げる
こうしたAI活用のスキルは、もはや“あると便利”ではなく“ないとまずい”領域になりつつあります。
とはいえ、全員が「技術職」になる必要はありません。
むしろ大事なのは、“人間だから出せるエッセンス”をどう込めるか。
- 自分の体験
- 心が動いた瞬間
- 読者への問いかけ
こういった感情や視点を言葉にする力が、ライターとしての“差別化ポイント”になります。
◆3. 双方に求められるのは「変化を受け入れる力」
最後に、広報担当にもライターにも共通して必要なのが、
“変わっていくこと”にビビらないマインドセットです。
生成AIは確かに驚異的ですが、敵ではありません。
むしろ、それを武器にできる人・組織がこれからの時代に選ばれていきます。
- 「AIを使ったことない」→「まず1記事やってみる」
- 「ちょっと怖い」→「怖がってる理由を知る」
- 「できる人に任せたい」→「自分でもやってみる」
完璧じゃなくてOK。
“変化に向き合う姿勢”そのものが、これからの最大の強みになるのです。
まとめ|「AIでいいや」じゃなく「AIだからこそ人が光る」時代へ
ライター業は終わるのか?
答えは、NO。ただし「形」は変わる。
たしかに、生成AIはライティングの世界に革命をもたらしました。
AIを使えば、安く、速く、そこそこの文章が手に入ります。
企業が「これもう外注いらなくない?」と思うのも、無理はありません。
でも、ここまで読み進めたあなたならわかるはずです。
本当に読者の心を動かすのは、やっぱり“人の言葉”だと。
そして、AIが当たり前になる今だからこそ、
「あ、これは人が書いてるな」と思わせる温度や視点、余白やユーモアが、一層輝くのです。
◆企業も、ライターも、次のステージへ
企業の広報担当者は、AI活用×人間らしさのハイブリッド体制を目指しましょう。
外注をなくすかどうかではなく、「どう再設計するか」が問われる時代です。
ライターは、“書くだけの人”から“価値を添える人”へ。
AIと並走しながら、言葉に血を通わせる役目が、これからもっと重要になっていきます。
◆変化の波にのまれるか、乗りこなすか
技術は止まりません。AIはますます進化します。
でも、それを恐れる必要はありません。
必要なのは、“無くなる仕事”に怯えることじゃなく、
“これからの自分に何を足していくか”を考えること。
生成AIは、ライターを淘汰するツールではありません。
むしろ、人間の創造性を拡張する最強のパートナーです。
だから私たちは、こう言いましょう。
「AIでいいや」じゃなく、「AIがあるからこそ、私はもっと書ける」って。
こんな時代だから遊んで学びたい

AIを学ぶオンラインサロン「AIフレンズ」では、生成AIを楽しく、どこよりも優しく学べる環境をご用意しております。
毎週開催されるオンラインセッションでは、リアルタイムで学び合える機会を提供しています。 さらに、月に一度のオフラインイベントでは、メンバー同士が直接交流し、アイデアや知識を深めることができます。
「AIフレンズ」の仲間とともに、新しい価値を創造し、可能性を広げてみませんか?
一緒に学び、成長しながら、生成AIを使いこなす力を身につけましょう!
遊んで学ぶ!完全無料のウェビナー開催中! 参加者限定豪華特典付き!
【AI難民必見!】90分で完結する次世代の生成AI人材に向けてのウェビナーイベント!
日時:2025年5月9日(金) 20:00〜21:30
会場:オンライン(Zoom)
5月20日秋葉原でオフラインイベント開催!!
生成AIについての体感型ワークショップを実施します。AIコンサルタントが解説フォロー!AIについて仲間とともに学び交流を楽しもう!!
【経営者・フリーランス必見!!】業務効率だけじゃない!生成AI活用ワークショップ
日時:2025年5月20日(火) 19:30〜21:30
会場:ふれあい貸し会議室 秋葉原No53